
芸工大の美術科彫刻コースで立体造形を学んだ桜井浩明(さくらい?ひろあき)さんは、卒業後、マネキンの制作?販売を手掛ける株式会社モード工芸に就職。以降、マネキン原型師として15年以上活躍されています。基本は粘土造形ですが、近年は3Dを用いたデジタルでの作業も行っているのだそう。今回は、マネキン原型師のお仕事の魅力とともに、芸工大で学んだことがどのように活きているのか? をお話しいただきました。
? ? ?
自分の手で直接、理想の形を作り上げていく魅力
――“マネキン原型師”というのは、具体的にどのような内容のお仕事なのでしょうか
桜井:アパレルブランドさんを対象に、弊社で新規に制作?販売するマネキンの企画を考えたうえで、その原型を粘土で造形しています。マネキンは、海外の工場で型をとって量産されるのですが、その大元となる原型を制作するのが私の仕事です。社内の商品開発会議で「どんな層をターゲットにするか」「そのターゲットに向けて、どのようなイメージで制作するか」を話し合ったうえで、実際にそれを形にしています。
また新規製作だけでなく、既存の商品の一部ポーズを変える“改造”を手がけることや、最近はアパレルブランドさんの展示会場にて施工を行うこともあります。

――一見同じように見えるマネキンでも、その裏側には企画会議があり、次々と新商品が生み出されているのですね
桜井:そうですね。マネキン単体でトレンドを表現するのはなかなか難しいことではあるのですが、ずっと同じマネキンだと、消費者の目が慣れてマンネリ化してしまうので。アパレルブランドさんのほうで定期的に店舗のマネキンを入れ替えて、目新しさを打ち出していく必要があります。
そのために「次は、どんなマネキンだと、アイテムの魅力が消費者に伝わるか」を考えて、新商品を企画しています。
――マネキンの原型制作を行ううえで、桜井さんが大切にしていることを教えてください
桜井:「お客さま(アパレルブランド)が求めているものをいかに表現できるか」、そして「そのなかに自分のこだわりを、どのように落とし込むか」を常に考えています。

マネキンはいわゆる商業美術なので、私個人の表現だけをするのではなく、お客さまの要望を汲み取って形にしなければなりません。そしてマネキンは服をディスプレイするためのものなので、服を着せた際の見栄えやサイズ感など、気をつけるポイントがたくさんあります。そういったポイントを踏まえつつ、限られたキャンバスの上で自分の「かっこいい」「かわいい」を形にしていくのが難しくもあり、この仕事の何より楽しいところです。
――そもそもマネキンの原型は、どのように作られているのでしょうか?
桜井:基本的には、まず木材に針金や棕櫚縄(しゅろなわ)を巻き付けた“芯棒(しんぼう)”というものでベースを作って、上から粘土を盛りつけています。そして、自分が思い描いている形となるように、粘土を削ったり盛ったり……を繰り返して造形していきます。
これは、大学時代に手がけていた塑像(そぞう)の制作工程と非常に近いんですよ。自分が学んできたものをダイレクトに活かせるという意味でも、非常に進めやすいですし、やりがいのある仕事ですね。
そのうえで近年は、会社のほうでデジタルでの作業となる3Dモデリングを導入するようになりました。私個人としては初めての3Dということで、勉強しながら仕事に落とし込む日々ではありますが、手作業と違う魅力があって面白いです。

――従来の手作業と3Dでの制作には、違いはあるものですか?
桜井:それぞれ、得意?不得意が異なります。まず手作業での粘土造形は、自分の手で直接形を作ることができますし、実物を間近で見ながら作業できるので、直感的なわかりやすさがあるのが最大の魅力です。
一方で3Dモデリングは、作業の“やり直し”やモデルの拡大?縮小がボタン一つで簡単にできるのが粘土造形との大きな違いです。そして先ほどお伝えした、芯棒や粘土などの準備が必要ないので作業が圧倒的に楽ですね。ただ、画面という平面上での作業になる関係で、3Dプリンターで実物を出力してみると、作業していたときの印象と少し違う……ということも起こり得ます。
このように、両者で特徴が異なりますので、両方体験してみた所感としては、それぞれの良さを取り入れて併用するのがいいんじゃないかな、と思っています。たとえば、大元のベースは粘土で造形したうえで、それを3Dスキャンして最終的な仕上げはデジタルで行う……といったイメージです。

――さまざまな業界でデジタル化が進んでいる昨今ですが、3Dモデリングをメインで行う方でも、従来の粘土造形を経験しておくこともやはり必要なのでしょうか
桜井:個人的には、そう思います。「自分の手で、粘土を触りながら形を把握していく」「“手と目”で量感を感じる」というのが、造形において大切なのではないかな、と。その体験によって、筋肉のつき方や人体そのものの形を直感的に学ぶことができるので。ですから、3Dモデリングに興味がある方も、まずは一度、手作業での粘土造形をやってみるとすごく勉強になると思いますよ。
ただ先ほどもお話ししたように、デジタルでの作業にも強みはあるので、粘土造形と3Dモデリング、両方できるようになるのが一番良い、と考えています。私自身、仕事がきっかけで初めて3Dモデリングに触れて、非常に魅力的な手法だと感じました。最初は「どこを操作したら、どうなるの?」といった具合だったのですが、操作に慣れると自分の表現の幅が広がる感覚があって、楽しかったです。
……ちなみに、それが高じて、プライベートでも3Dを使ってフィギュアの制作にチャレンジしてみたんです。フィギュアの展示?即売会である『ワンダーフェスティバル』に出展して来場者と交流したのですが、新鮮で良い経験になりました。

高校卒業間際に出会った彫刻、そして芸工大の魅力
――桜井さんは千葉県出身ですが、どのような理由で芸工大への進学を決められたのでしょうか
桜井:元々自分は、東京学館総合技術高等学校(現?東京学館船橋高等学校)で高校時代から美術を専攻していて、ある日学校に芸工大の出張説明会が来たんです。そこで芸工大の存在を知ったのですが、説明を聞いて心を掴まれて、「面白そうな大学だな」と思いました。関東には美大がたくさんあるので、芸工大に行かずとも美術は学べます。しかも千葉から山形は、それなりに距離があります。ですがそんなことは全く気になりませんでした。とにかく、芸工大への興味が先行していたんです。
それでオープンキャンパスに足を運んでみたら、まず山形の豊かな自然に感動し、さらに芸工大本館のモダンなかっこよさに大興奮しまして(笑)「絶対に、ここに入りたい!」と思って受験を決めました。
――高校でも、彫刻をやられていたのですか?
桜井:いえ、高校では陶芸をやっていました。高校生活ではずっと器を作っていたのですが、卒業制作で、粘土を使って人形を作ってみたんです。そうしたら当時の先生に「お前、彫刻のほうが向いているんじゃないか?」と言われて、そこから彫刻に興味を持つようになりました。
芸工大のオープンキャンパスでも、美術科彫刻コースを見てみて、手の塑像体験に参加させていただいたんですね。それで「彫刻って、楽しい!」と思って、彫刻の道に進むことを決めました。その結果、こうして今の仕事につながっているので、あのときオープンキャンパスに参加して本当によかったと思います。彫刻という選択肢を示してくださった、高校時代の先生にも感謝しています。

――芸工大で学んだ内容で、今のお仕事にも活きているものはありますか?
桜井:はい。学生時代に教わった、造形への向き合い方は仕事の際にも大切にしています。
塑像を制作するときって、どうしても目や鼻といった表面の形状ばかりを追ってしまうのですが、実はそれではダメなんですよ。当時の教授に「もっと重心や骨格、バランスを意識して、“地に足がついている”造形を目指そう」と言っていただいたことが印象に残っていて。今でも、原型を制作する際は美術解剖学の本や参考写真を見ながら、表面の形状の奥にある、芯の重心や骨格を意識しています。
ちなみに、マネキンは彫刻と違って、実は“地に足がついていない”んです。なぜかというと、あとから靴を履かせる必要があるからですね。特に女性のマネキンの場合、ヒールのぶん、かかとがかなり上がっています。そこが大学時代に制作していた彫刻とは大きく異なります。ただ、靴を履いているのと変わらないバランスで制作するには、“地に足のついた造形”を理解している必要がありますので、やはり大学での学びは非常に重要でしたね。

――それでは最後に、芸工大の受験を考えている受験生へメッセージをお願いします
桜井:芸工大は、山形のあたたかい人や地域とのつながり、広い空や美しい景色を感じながら制作に没頭できる、最高の大学です。自分の風呂敷を大きく広げて思うがままにやってみたら、それを全部受け止めて、未来へ導いてくれるような場所だと思っています。ですから、やりたいことへの情熱のある方、抑えきれない想いのある方には芸工大はピッタリだと思います。型にとらわれず「できないことなんて何もない!」という気持ちで、自分の好きなことに向かって突き進んでいってほしいです。
芸工大のある山形は、都心とは違う時間の流れさえも感じるほど、穏やかで心地よい場所なんですよ。あの場所で4年間を過ごして芸術を学べるって、すごく幸せなことだなぁ……と、卒業してから、より一層感じるようになりました。一度オープンキャンパスに行ってみて、現地でなければわからないその魅力を、ぜひ感じていただきたいですね。

? ? ?
「山形は第二のふるさと」と語る桜井さん。山形の自然に囲まれて学んだ造形の技術を用いつつ、今後はこれまでの手法と3Dモデリングを融合させて、さらなるスキルアップを目指しているとのこと。仕事で学んだ技術をプライベートにも活かし、造形への興味が公私ともに良い影響を生み出しているのは、芸術を学んで社会に出た芸工大卒業生にとって理想の姿だと感じました。
(撮影:永峰拓也、取材:城下透子、入試課?須貝)
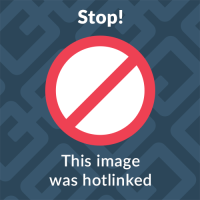
足球比分|直播_皇冠体育-篮球欧洲杯投注官网推荐 広報担当
TEL:023-627-2246(内線 2246)
E-mail:public@aga.tuad.ac.jp
RECOMMEND
-
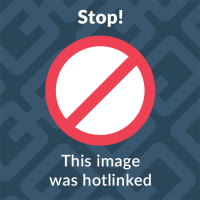
2023.03.03|インタビュー
人との関わりに喜びを感じ、社会の中でアートを生かす /社会福祉法人「愛泉会」?卒業生 髙力了生
#卒業生#総合美術 -
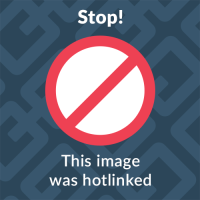
2020.09.01|インタビュー
現代アートでよみがえる「藻が湖伝説」のリアリティ/三瀬夏之介(山形ビエンナーレ2020 プログラムキュレーター)
#山形ビエンナーレ#教職員 -
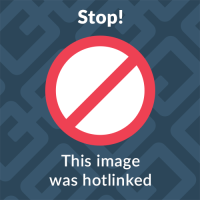
2020.01.09|インタビュー
そして、彼女はマタギになった…/卒業生 マタギ?小国町役場 蛯原紘子
#卒業生#日本画#歴史遺産




